 |
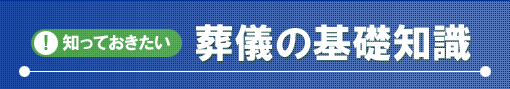 |
| 葬儀の基礎知識の目次に戻る |
出棺から精進落しまで別れ花と石打ち葬儀後、出棺のためにお棺を祭壇からおろします。祭壇などに供えた花を遺族と親しい縁者の方がご遺体の周囲に捧げます。これを「別れ花」といいます。 対面後、お棺のふたをしめるために、小石で釘を打ちつけます(「石打ち」、「釘打ち」)。小石には無事に三途の川を渡り成仏できるようにとの祈りがこめられています。
出棺お棺は、近親者、親しい友人・知人の男性が霊柩車まで運びます。 火葬場へ喪主、遺族、故人と近い関係の順で分散乗車して火葬場へ向かいます。この時、僧侶にも同乗してもらうことが多いようです。 納めの式と火葬「納めの式」とは、火葬炉の前の祭壇にお棺を安置して、故人と最後のお別れをすることです。 骨あげ(拾骨:収骨)「骨あげ(拾骨)」の作法には、二人が一組になり一緒にひとつのご遺骨を拾い骨壷に納める作法と、二人のうち一方がご遺骨を拾い上げ、もう一人の方へと渡しその方がご遺骨を骨壷へと納める作法とがあります。 分骨分骨を希望する場合には、あらかじめ葬儀社の担当者に伝えておきます。分骨用の骨壷を用意しておくことになります。 「埋葬許可証」の受け取り「骨あげ」の後、事前に提出した火葬許可証に火葬済みの証明印が押された書類を受け取ります。 遺骨のお迎え留守居役は、お棺を見送った後「遺骨迎え」の準備をします。 ※浄土真宗ではお清めを行いません。また、地域、宗派により異なります。 中陰檀とあと飾り留守居役は、ご遺骨をお迎えするため「あと飾り」をした「中陰檀」を準備します。 繰上げ初七日法要最近では、葬儀後七日目に行う初七日法要を、火葬場から戻るとすぐに行ったり、葬儀・告別式のすぐ後に行うことが多いようです。 精進落とし(お斎)葬儀を終えた後に会食を行いますが、これを一般的に「精進落とし」または「お斎(とき)」と呼びます。 故人との最後の交わりをして別れをするという本来の意味に加え、参列していただいた方への感謝の気持ちを込めて振る舞うという意味もあるようです。 |
