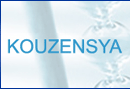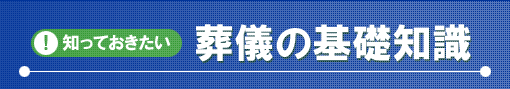香典について
香典袋の書き方
仏教の場合
葬儀の時の一般的な表書きは「御霊前」ですが、浄土真宗の場合は「御仏前」と書きます。
「御香典」「御香料」と書く場合もあります。黒白の水引を使います。
※忌明け(四十九日)後の法要の表書き
「御仏前」と書きます。「御供物料」と書く場合もあります。
神道の場合
銀の水引を使って、「御玉串料」と書くことが多いようです。「御榊料」「御神饌料」などと書く場合もあります。
キリスト教の場合
「献花料」「御花料」などを書きます。水引はなくてもかまいません。
グループで包む場合
二人で一緒に包む場合は、下段にそれぞれの氏名を横に並べて書きます。
グループで包む場合は、半紙などにメンバー全員の氏名を書き、中袋に入れます。
表には「○○会有志」あるいは会社名や部課名などを書きます。
金額の目安
香典の金額は、故人にお世話になった度合いによって違いますので、一概には言えませんが、一応の目安はあります。
一般的には、血のつながりが濃いほど高額になり、両親の場合には十万円、兄弟で五万円、その他の親戚の場合一万円が多いようです。
職場の上司や同僚、近所の方、友人の場合には五千円が目安です。
香典の包み方
香典袋を折る場合は、左手前に折ります。
そして下側を折り、その上に重なるように上側を折ります。
お札は、あらかじめ用意してあったようでは失礼ですので新札は使いません。
新札しかない場合には、一度折り目を入れてから包みます。
そして地味な色のふくさに包んで持参します。
ふくさの包み方は、まず香典袋を表にして中央に置き、右、下、上の順にたたみます。
香典を郵送する場合
通夜・告別式ともに出席できない時には、現金書留で香典を郵送します。
この場合、まず現金を香典袋に入れてから、現金書留の封筒に入れます。
その際、出席できない理由と、故人を偲ぶ手紙を添えた方が心がこもるでしょう。
香典の出し方
香典は、遺族の方が後で整理しやすいように出すことが重要です。
住所や氏名は見やすいように書きたいものです。
また、金額もはっきり書くようにしましょう。
ご霊前に供える場合
表書きが自分から読める方向にして供えます。
受付で渡す場合
受付などで係りの方に渡す場合は、係りの方が読める方向にして渡します。

|