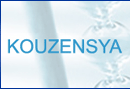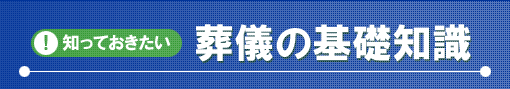あいさつ回り、法要など
挨拶回り
葬儀後、2〜3日中に「挨拶回り」へ赴きます。
訪問先には事前に連絡しておいた方が良いでしょう。
- 寺院など
- 世話役代表とお世話いただいた方
- 親戚
- 近所の方
- 故人と特に親しかった方
- 会社関係の方 など
故人の勤務先への挨拶回りは、公的手続きも同時にすることになりますので、事前連絡の際、用意するものなどを確認しておきます。
- 身分証明書
- 会社の鍵やバッチ
- 社会保険証、厚生年金手帳
- 印鑑
勤務先では、「給与、退職金、持ち株、団体保険や埋葬料、遺族年金」などの支払準備を進めます。
死亡通知とお礼状
通夜、葬儀の連絡がとれなかった方へ、「死亡通知」を送ります。また、通夜・葬儀後、一般参列者の方に「会葬礼状」を渡していない場合には、早めに「会葬礼状」を送ります。
基本台帳の整理と作成
葬儀後、「死亡通知」「お礼状」「香典返し」「法要」「補助金申請」「遺産相続」「税控除」「確定申告」などの諸手続きを滞りなく行うため、基本台帳を整理・作成します。
- 芳名帳 (名刺なども一緒にします)
- 広範な関係者名簿 (死亡通知、年賀欠礼挨拶状などのため)
- 香典帳 (供物帳、香典袋なども一緒にします)
- 会計記録台帳 (各種領収書も必ず整理しておきます)
忌中と喪中
「忌中」とは、仏式では「四十九日」の忌明けまで、「喪中」は、故人が亡くなってから1年後の命日までです。喪中の間、遺族は慶事・祭礼などへの出席を差し控えます。
仏式の法事は「中陰供養」と「年忌法要」とに分かれます。
「中陰」とは故人の来栖が決まるまでを指し、亡くなられた日から四十九日までです。その忌明けまで7日ごとに法要を行う日がおとずれます。
- 初七日(しょなのか) 亡くなられた日を含めて7日目
- 二七日(ふたなのか) 亡くなられた日を含めて14日目
- 三七日(みなのか) 亡くなられた日を含めて21日目
- 四七日(よなのか) 亡くなられた日を含めて28日目
- 五七日(ごなのか) 亡くなられた日を含めて35日目
- 六七日(むなのか) 亡くなられた日を含めて42日目
- 七七日(なななのか) 四十九日、忌明け、満中陰
四十九日(七七日)は中陰供養の中でも特に大切なものです。僧侶にお願いして、丁寧に忌明け法要を行います。
宗派によって五七日(三十五日)をもって忌明けとする場合もあるようです。また、本来の法事の日に都合がつかず、別の日に振り返る場合には、遅らせずに早めに済ませましょう。
他に百ケ日法要も重要で、死後100日目にあたる日に行います。
ただし、地域、宗派により内容が異なることがあります。

納骨
自宅に安置するご遺骨は、「四十九日」「百ケ日」遅くとも「一周忌」までに納骨します。
「納骨法要」には、親戚や故人と親しかった方に出席をお願いし、僧侶にお勤めをしていただきます。
線香、ろうそく、お花、桶、柄杓、供物などを用意しておきます。
※埋葬の祭、埋葬許可証を墓地のある寺か霊園の管理事務所に提出します。印鑑が必要です。
墓地の名義人が故人となている場合は、名義変更が必要です。
一周忌
故人が亡くなられてからちょうど1年後の同月同日(=祥月命日 ショウツキメイニチ)に行います。
喪中期間はこの日で終わります。
僧侶の読経、列席者の焼香などで故人の供養をします。
年忌法要
三回忌は故人の死後、3年目ではなく、満2年目に行います。
同様に、七回忌は、6年目、十三回忌は、満12年目、三十三回忌は、満32年目となります。
弔い上げ
本来、先祖供養は「何年やったから終わり」ということではありませんが、一般的には三十三回忌を最後の法要として、「弔い上げ」とする場合が多いようです。
その際、位牌は「○○家先祖の霊」として合祀することになります。その後は、お盆やお彼岸に供養する形となります。
|